9月11日のカタストロフ(破局)とバックラッシュ(反動)を持ちこたえた700万人のムスリム(そのうちの200万人だけがアラブ人だ)にとって、この間は痛ましくとりわけ不愉快な日々であった。残虐な行為によって無実のアラブ人やムスリムに犠牲者が出ただけではない。それに加えて、アラブ人やムスリムのグループ全体に向けられた明確な憎悪の空気がさまざまな形で出てきているのである。ジョージ・ブッシュはすぐさま「アメリカ」と「神」とを同列に並べ、そしてこの恐るべき行為を犯した「人々」--ブッシュは「生死を問わず」と言っている--に対して宣戦布告をした。そしてこのことが意味しているのは、もうこれ以上思い起こす必要もないことだが、ウサマ・ビン=ラーディンという捕らえどころのないムスリム狂信者が大多数のアメリカ人にとってイスラームを代表する人物であり、その彼が舞台中央を占めたということである。テレビやラジオはほとんど絶え間なく彼の資料映像を流し、影の多い(以前は「道楽者」だと言っていたのに)過激派であるという説明を植えつけている。同時にマスコミは、アメリカの悲劇を「祝っている」ところを撮られたパレスチナ人の女性や子どもたちの映像を植えつけているのだ。
評論家や番組司会者らは何度となく、イスラームに対する「我々」の戦争だと言い、「ジハード」や「テロ」といった言葉が、国じゅうに広まっているもっともな不安や怒りをいっそう狩り立てている。すでに二人の人間(一人はシーク教徒)がかっとなった市民らによって殺されたが、殺した人は、国防省役人のポール・ヴォルフォヴィッツなどが言っている「国を潰す」とか「敵を殲滅する」といったコメントを字義どおりに考えるように助長されているようだ。何百人ものムスリムやアラブ人の商店主や学生や、ヘジャブをかぶった女性、そして一般市民が、侮辱の言葉を浴びせられた。他方で、ムスリムやアラブ人に死を迫ることを告知するポスターや壁書きがいたるところに現われている。ある主要なアラブ系アメリカ人組織の指導者が今朝私に言ってきたところによると、侮辱や脅迫や血も凍るような言葉による攻撃のメッセージの数は平均一時間に10にも及ぶそうだ。昨日発表された世論調査によると、「アラブ人はアメリカ市民であっても特別な身分証明書を携帯するべきである」という考えに対しては、49パーセントが「はい」と答え(49パーセントは「いいえ」)、「アラブ人はアメリカ人であっても特別な、より厳しい安全検査を全員が受けるべきである」ことを58パーセントが要求している(41パーセントはそうではない)。
その後、公的な敵意は徐々に小さくなっていったのだが、それは同盟諸国が自分と同じようにはまったくの無遠慮ではないということにジョージ[ブッシュ大統領]が気づいたからであり、また(疑いなく)いくつかの助言があったからである。いく人かの助言者、その筆頭は全体的により分別があるように見えるコリン・パウエルだが、彼らは、アフガニスタンに侵攻することはテキサスに国民軍を送ったときほどには単純ではないと提言した。さらにまた、ジョージと彼のスタッフにのしかかった異様に混乱した現実によって、彼がずっと国民を代表して主張してきた「善対悪」という単純なマニ教的[二元論的]イメージが追い散らされてしまったということも、公的な敵意の減少につながっている。もちろん警察やFBIによるアラブ人やムスリムに対する嫌がらせの報告はいまでも氾濫しつづけているが、この顕著な敵意の縮小は始まっている。ブッシュ大統領はワシントンのモスクを訪れた。また地域コミュニティのリーダーと議会に憎悪のスピーチを抑制するように求めた。そして、「我々の」アラブ人やムスリムの友人(通常はヨルダンとエジプトとサウジアラビア)と、まだ明らかにされていないテロリストとを、少なくともレトリックとしては区別するように努め始めた。上下両院合同本会議の演説で、ブッシュ大統領は確かに、アメリカはイスラームと戦争をするのではないとは言ったが、しかし残念ながら、国じゅうでムスリムやアラブ人や中東出身者に似ている人々を次々と襲っている、事件[暴行・殺人]や言辞[侮蔑]の波については一言も触れなかった。パウエルはイスラエルとシャロン首相がパレスチナ人をいっそう弾圧するのにこの危機を利用していることに不快感をあちこちで表明しているが、全体的な印象としてはアメリカの政策はあいかわらず以前と全く同じコースの上にある――つまり大規模な戦争が準備中であると思われるのは今だけなのだ。
しかし、アラブ人とイスラームについて流布している極端に否定的なイメージとのバランスをとって、よりどころとすべき肯定的な知識が公的な空間にはほとんどない。つまり、好色で、執念深くて、乱暴で、不合理で、狂信的な人々というステレオタイプがともかくも持続しているのだ。大義(原因)としてのパレスチナはここ[アメリカ]ではまだ人々の想像力をとらえていない。ダーバン会議[反人種主義・差別撤廃世界会議]以降はとりわけそうだ。私の大学は知的多様性と学生・スタッフの異質性で有名なのだが、そこにおいてさえ、クルアーン[コーラン]のコースに申し込む学生はめったにいない。フィリップ・ヒッティの『アラブ民族の歴史』という、この分野で英語で読めるものとしては現代的で一巻本でありはるかに最良と言えるの本なのだが、絶版となっている。入手可能なものはたいてい論争的で敵対的なものばかりだ。アラブ人とイスラームとは論争の対象であって、他のものと違って文化的なあるいは宗教的なテーマにはならないのである。映画やテレビには、恐ろしく無愛想で残酷なアラブ人のテロリストが満ち溢れている。彼らはすでにそこにいたのだ。ワールド・トレード・センターと国防総省に突っ込んだテロリストたちが飛行機をハイジャックしそれを大量殺戮の道具にしてしまう以前から。今度の事件は、いかなる宗教よりもずっと犯罪的な病理の臭いがする。
活字メディアの中には、「我々はいまやみなイスラエル人である」というテーゼを家庭の中に叩き込む、あまり大きくはないキャンペーンがあるようだ。そして同時にこのキャンペーンは、パレスチナ人の自爆という方法で時折起こることは、規模の大小はあれど、ワールド・トレード・センターと国防総省への攻撃とまったく同じなのだというテーゼをも叩き込む。この過程で、パレスチナ人の収奪と弾圧はたんに記憶から消し去られてしまう。そして同じく消し去られてしまうのは、自爆に対する多くのパレスチナ人による非難の声である。この非難には、今回の自爆だけでなく自分たちのものも含まれているのだ。こうして全体の帰結として生じることは、9月11日に起こったことの恐怖をアメリカの行為やレトリックの文脈の中に置きなおそうというあらゆる試みが、テロリストの自爆をどうにかして許すものだとして攻撃されたり退けられるということなのだ。
知的にも道徳的にも政治的にも、このような態度は破滅的である。というのも、理解することと許すこととを同一視することは根本的に間違っており、真実からははるかにかけ離れているのだから。たいていのアメリカ人が信じるのが困難なことは、中東とアラブ世界におけるアメリカの国家としての行動である--列挙すると、イスラエルに対する無条件の支援。イラクに対する制裁。これによってサダム・フセインが助けられ、何十万人もの無実のイラク人が死や病気や栄養失調に追い込まれている。スーダンへの爆撃。1982年のイスラエルのレバノン侵攻への「青信号[ゴー・サイン]」(この時、サブラとシャティーラの虐殺以外にも、約2万人もの市民が命を落としている)。アメリカの私的な領地としてサウジアラビアとペルシャ湾を使うこと。抑圧的なアラブやイスラームの体制を支援すること--これらすべてのことは、ひじょうに憤激を買っているのだが、不適切にもアメリカ国民の名のもとで行われていることだとはみなされていないのである。平均的なアメリカ人知っていることと、海外で実施されているしばしば不当で冷酷な政策との間には莫大なギャップがある。これはアメリカ人が意識していようと、していまいとそうなのだ。イスラエルの入植地や市民への爆撃などなどに対する国連安保理の非難決議にアメリカはことごとく拒否権を行使しているが、そのことは、例えばアイオワやネブラスカの住人たちからは、取るに足りない出来事として、もしかすると当然のこととして無視される。他方で、エジプトやパレスチナやレバノンの市民にとっては、このことは極度に傷つける行為であって、極めて厳密に思い起こされる。
言い換えれば、一方でアメリカの特定の行為と他方その結果としてのアメリカに対する態度[アメリカに対する憤激]の間には、矛盾論理があるのであって、この態度[憤激]は、アメリカの繁栄や自由など世界中のあらゆる成功に対する嫉妬や憎しみといったものとは文字どおりほとんどまったく関係がない。それどころか、私が話をしたことのあるあらゆるアラブ人とムスリムは、どうしてアメリカほどの途方もなく裕福で賛嘆すべき国家(しかも個々のアメリカ人のグループはとても好感が持てるのに)が他国民に対して冷淡なまでに関心を払わずに国際的に振る舞っているのかについて当惑を表明している。そしてまた確かなことは、多くのアラブ人とムスリムが状況を自覚的に把握していることだ。つまり、親イスラエル・ロビーによるアメリカの政策について、『ニュー・リパブリック』や『コメンタリー』といった親イスラエルの出版物恐るべき人種主義と猛烈な怒号について、そして言うまでもなくチャールズ・クラウトハンマーやウィリアム・サファイア、ジョージ・ウィル、ノーマン・ポドホレッツ、そしてA.M.ローゼンタールといった血に飢えたコラムニストたちについて理解しているのだ。彼らのコラムは、いつもアラブ人とムスリムに対して憎悪と敵意を表明している。これらはたいてい主流のメディアの中に見つけることができる(例えば、『ワシントン・ポスト』の社説ページなど)。そこでは誰もがそうしたコラムをそれとして容易に読むことができるようになっており、周辺的な記事として後ろのページに埋もれてしまうことがないのだ。
 |
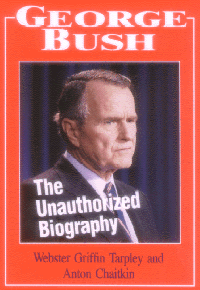
|
それゆえ我々キい感情と深い懸念の時代を持ちこたえているのであり、より多くの暴力とテロリズムの約束が意識を支配している。とりわけニューヨークとワシントンではそうなのだが、そこでは9月11日の恐るべき残虐行為がいまだに生々しく自覚されているのだ。私は確かに創感じるし、私の周囲の人々も同じように感じている。
しかし、にもかかわらず勇気づけられるのは、ぞっとするような一般メディアの報道にもかかわらず、平和的な解決と行動を求める異議や請願が少しずつ現われ始め、まだまだまばらだとしても徐々に広まっており、爆撃や破壊に代わる代替策への要求が相対的には小さくとも出てきたことである。この種の思慮深さは私の見解ではひじょうに注目に値する。まず第一に、政府の要請に応じて、市民の自由と個人のプライバシーに対する侵害が見られ、そしてテロの容疑で中東[出身]の人々を電話を盗聴し、逮捕し拘留する権限の強化、さらに警戒と疑いと動員という状況を一般的に引き起こすというマッカーシズムに似たパラノイアが見られる。これらに対する懸念がひじょうに幅広く表明されている。どのように読み取るか次第では、アメリカ人がいたるところで国旗を振る慣習はもちろん愛国的にも見えるが、しかし、愛国主義は不寛容さ、ヘイト・クライム[憎悪による犯罪]、そしてあらゆる種類の不快な集団的情熱に結びつく。多くの解説者らがこのことを警告しているし、私は以前から言ってきたことだが、大統領でさえも演説で、「我々」はイスラームやムスリムの人々と戦争をするのではないと言明した。だが、危険はすぐそこにあるのであって、このことは幸運なことに他の多くの解説者によっても適切に指摘されている。
第二に、軍事行動の問題全体に焦点を当てた多くの呼びかけや集会がある。こうしたものは、最近の世論調査では92パーセントのアメリカ人が望んでいる。しかしながら、行政当局からこの戦争の目的は何なのか(「テロリズムを根絶すること」は実際的というよりは形而上学的である)もまた計画も明確に具体的に述べられていないため、軍事的に我々がどこに行こうとしているのかについてかなりの不確かさがある。しかし、一般的に言って、レトリックは黙示録的でも宗教的でもなくなってきており--「十字軍」という考えはほぼ完全に消えた--、より焦点が当てられてきているのは、もう「犠牲」だとか「他のいかなる戦争よりも長期の戦争」といったような一般的な言葉ではなく、何が必要なのかということになってきている。大学やカレッジ、教会、公会堂では、国家は対応として何をすべきなのかについてひじょうに多くの議論がなされている。無実の被害者の遺族が「軍事的報復は適切な対応ではない」と公然と言ったのさえ私は聞いている。ポイントは、アメリカが何をなすべきかについてのかなりの熟考が全体になされているということなのだが、しかし残念ながら、アメリカの対中東政策や対イスラーム世界政策についての批判的検討の時期はいまだに訪れてはいない。私はその時期が来ることを望んでいる。
世界に対する主たる長期的な希望が良心と理解の共同体であること、憲法上の諸権利を守るときであれ、アメリカの権力による無実の被害者(イラクの人々のような)に手を差し伸べるときであれ、理解と理性的分析にたよるときであれ、良心と理解の共同体が希望であることを、もしより多くのアメリカ人と他の人々がしっかりとつかんでさえくれたなら、「我々」はこれまでしてきたよりもずっとうまく振る舞えるはずだ。もちろん、このことが直接にパレスチナに対する政策変更や、防衛予算の歪みの是正や、環境問題やエネルギー問題に対する姿勢の啓発につながるわけではない。しかし、この種の慎み深いバックトラック(是正)以外に、希望の余地はあるだろうか? もしかするとこうした有権者らがアメリカで育ちつつあるのかもしれない。だが、パレスチナ人としてしゃべるならば、私はまた同じような有権者らがアラブ・ムスリム世界でも現われることを希望しなければならない。「我々の」社会を支配するようになった貧困、無知、文盲、抑圧、そしてシオニズムや帝国主義に対する我々の不満の訴えにもかかわらずその跳梁を許してしまった悪について、我々自身に責任があると考え始めなければならない。例えば、我々のうちのはたして何人が、「世俗的な(非宗教的な)」政治を率直に誠実に擁護してきただろうか?何人が、イスラエルや西欧においてユダヤ教やキリスト教を巧みな操作していることを我々が告発してきたのと同じように、イスラム世界での宗教の利用を徹底的にそして熱心に批判してきただろうか? そして我々のうちの何人が、あらゆる自殺的な活動を非道徳的で間違っていると非難してきただろうか--たとえ我々が、植民地的入植者や非人道的な集団的懲罰による荒廃に苦しんできたとしても。我々はもはや我々に対してなされた不正義の後ろに隠れたりはしないし、もはや我々の不人気な指導者らをアメリカが支援することをただ受動的に嘆き悲しむこともしない。新しい「世俗的な」アラブの政治を知らしめなければならないし、一瞬たりとも見境なく殺そうとする人々の戦闘を認めたり支持してはならない。この点に関してはいかなる曖昧さも存在しないのだ。
私が何年ものあいだ主張してきたのは、我々が今日アラブ人として持っている主たる武器は、軍事的なものではなく倫理的なものであるということ、南アフリカでのアパルトヘイトに対する闘争とは異なって、イスラエルの弾圧に対してパレスチナ人の自己決定を求める闘いが世界中の人々の想像力をつかまえられない理由は、我々の目的と方法が明確であると見えないためだということと、そして我々の目標が共存と包含であり、決して排他主義や牧歌的で神秘的な過去への回帰ではないと十分はっきりと述べてこなかったためだということである。我々が率直になりすぐにでも自分自身の政治を検討・再検討・反省すべき時が来た。それは多くのアメリカ人やヨーロッパ人が今しているようにである。我々は他人について期待するのと劣らず自分自身についても期待しなければならない。そうすれば、指導者たちが我々をどこに導こうとしているのか、そしてそれはどういう理由からなのかを、すべての人々が十分に時間をかけて見ようとするだろう。懐疑精神と再評価が必要なのであり、贅沢が必要なのではない。訳注1:backlash(=反発、反動)とは、テロ直後のブッシュをはじめとする政治家やメディアや国民の直情的な反アラブ・イスラーム的な反発であり、backtrack(=撤回、修正)とは、その直情的な対応を是正しようという動きである。
************************************************
▲このページの先頭へ




