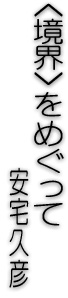| <目覚めよ、と呼ぶ声が聞こえ……> 眠りから醒めるとき、自分が泣いていたことに気づくことがある。夢のなかで、誰かに別れをつげでもしていたのか? 夢の内容は思い出すことができない。しかし、手の甲や頬には涙のあとが残り、それどころか瞼がまだ涙で潤んでいる。 そもそも、人はなぜ泣きながら生まれるのか。生と未生との境界で、赤ん坊は誰と別れを告げてきたのか。 塚本敏雄の「旅立ち」(『英語の授業』書肆山田)は、旅行の終わりになぜかいつも涙を流す娘にこう呼びかける。 そんなことが何度もあるうちに しかし、この詩のタイトルは、「旅の終わり」ではなく「旅立ち」とされている。旅の終わりに流す涙は、同時に旅のはじまりを刻印しているのだろうか。
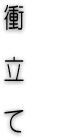 『英語の授業』が、<異界>
と <境界>をめぐる詩集であることは、誰の目にも明らかだろう。そこには例えばこんな言葉がつづられている。 『英語の授業』が、<異界>
と <境界>をめぐる詩集であることは、誰の目にも明らかだろう。そこには例えばこんな言葉がつづられている。 中学のとき数学の先生に (中略) 先生 「衝立て」を隔てて二つの世界があり、二つの異なる現実がある。その鋭い断面を詩人は鮮やかに、しかし、とぼけた調子で描き出す。この
<複数の世界の共存> というモチーフは、実は第二詩集『リーブズ』からひきつがれたものであり、 それが哲学では「可能世界論」、SFでは「並行世界」というアイディアに通底するものであることは、先に指摘した通りである。 また、「走りながら」では、突然「ねえ、私ってワガママ?」と聞いてくる <女性> もまた異界の住人である。そんな風に、 <異界> と私たちの <現実> を分かつ境界は、「下敷きで作った衝立て」のように日常のなかに偏在し、いたるところで姿をあらわす。 しかし、いたるところでその姿の片鱗を目にしているにもかかわらず、異界の住人と私たちはついに出会うことはない。その悲しみと、そして異界の人に感じる遠い懐かしさの感覚が、『英語の授業』の基調の旋律をなしている。 「彼ら」とはいったい誰だろう 遠い空の下 ――――――「英語の授業/人称について」 レヴィナスを想起するまでもなく、 <顔> の見えない人に対して、私たちは関心や責任を覚えることができない。しかしそれでもなお、「彼ら」のもとに「砲弾が降り注ごうとしている」とき、私たちはそのことに無関心・無責任でいられることの「峻別の酷さ」に思いをいたさないではいられない。
カントがそのことを宣言してから 200年余りがたつ。しかし、それがどんなに飛んでもないことか、私たちは本当に受け止めているのだろうか。 カントのその狂気めいた考察がもたらした波紋は、フロイトによる <無意 識> の発見に及び、20世紀のラカンによって <現実界><想像界><象徴界> という概念が生み出されるに至った。 言語によって秩序だてられた <象徴界> に住むわれわれは、せいぜいイメージによって構成された <想像界> を垣間見ることができるぐらいで、現実そのものである <現実界> には触れることができない。 しかし、ラカン理論の伝道者スラヴォイ・ジジェクは、『斜めから見る』
『…不愉快な職業』の登場人物ランドルは、仕事の依頼人であるホーグ氏から飛んでもない <真実> を聞かされる。「われわれ人間の住む宇宙は、存在しているさまざまな宇宙のひとつにすぎない。すべての世界の真の支配者は、われわれの知らない神秘的な存在たちで、彼らがさまざまな宇宙を芸術作品として作り上げるのだ。われわれ人間の住む宇宙も、そうした宇宙の芸術家の一人によって作られた(ジジェクによる要約)」。そしてホーグ氏は、自分もその宇宙の芸術家の仲間だと言い、今この人間が住む宇宙はちょっとした修理中なので、帰りの車中、決して車の窓を開けないようにとランドルに注意する。しかしその注意にも関わらず、ランドルは帰宅の途中で車の窓を開けてしまう。そこで見てしまう光景が、上記の記述だ。 そこでジジェクは指摘する。
しかし、私たちがついに <物自体> や <現実界> にふれ得ないものであったとしても、私たちはどこかでその存在を感じ、いつか見た遠い記憶のようにそれを求めないではいられない。プラトンの想起説が依拠するものも、そうした感覚である。ただしプラトンはその異界(イデア界)を故郷のように実在するものと考えたが、私たちはそれが実在する <ふるさと> でありえないことを知っている。 「帰ろう」の <ぼく> は、15歳のときに交通事故で死んだ息子の代わりに、<博士> が作ったロボットである。彼の記憶は、博士の息子の記憶をインプットした偽の記憶であり、そのことを彼は知っている。しかしそれでもなお、彼の口からは「帰ろう」という言葉がこぼれ出てしまう。 帰ろう ――――――「帰ろう」 そして、こんな詩句。 例えばあらゆる場所が 永久に留まることのできるものではないように ――――――「Reunion」
それは、異常なことでも神秘的なことでも何でもない。例えば、誰もが目にしているはずの「チョコボール向井」が、社会からは不可視の存在とされているように、私たちは現に目の前に見ているはずのものを不可視の領域に追いやってすごしているではないか。 例えば、1945年の敗戦直前、東洋経済新報社の主幹だった石橋湛山は、ある会合に出席した。そこでは、ヤルタ会談の結論を受け入れるかどうかということが議論され、参加者の多くは、「受け入れれば、日本は植民地を放棄し四島だけでやっていかなければならない。そんなことができるか」と疑問視していた。そのなかで湛山はひとり、「日本は四島だけでもやっていけるし、やっていく体制を作らねば」と説いたというのだが、このエピソードを聞く現代の私たちは、湛山の先見の明に感心するよりもむしろ、他の人びとが、植民地を放棄すれば国家が経営できなくなると本気で考えていたことに驚く。今日の私たちからは、日本が <四島> で成り立っているのは自明のことのように思えるからだ。しかし、そのことは、当時の <日本人> にとっては不可視だった。 そんな風に、人はいつも、明らかにそこに見えているはずのものを見ることができないでいる。それを思えば、北朝鮮の核武装への <制裁> が叫ばれ、自衛隊や日米軍事同盟の存在を自明のこととして受け入れている私たちにとって、見えていないものとは何だろうか。例えば <沖縄> を、私たちは本当に見たことがあるのだろうか。 だからチョコよ ――――――「チョコボール向井に」
ことしは息子の三十回忌だから ――――――「盆の月」 ――――――「英語の授業/現在完了」 ぼくは帰りの車の中でハンドルを握りながら ――――――「せんきゅうひゃく」 死者はなぜ回帰するのか。 先日、終末期患者の介護に熟練したある看護師に話を聞く機会があった。 死は誰にでも起こりうる。だから本来は痛み悲しむべきことではない。 死は誰にでも起こる。しかし私たちは誰も死を知らない。 死は不可視である。 それでもなお、死者が生きる私たちから顔を背け、不可視の世界へ帰っていこうとするとき、私たちは切なさに嗚咽の声をあげないではいられないのだ。
大きな池のようなものが見える ――――――「水のほとりで」 2006年11月6日号掲載 |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
 私たちの認識は <物自体> を捉えることができない。
私たちの認識は <物自体> を捉えることができない。 私たちは
<不可視なもの> に取り囲まれ、それを見ることができないでいる。そして、目に見えるかぎりのものを <現実>
と呼んですませている。しかし、そんなものが本当に <現実> と呼ぶに値するのか。
私たちは
<不可視なもの> に取り囲まれ、それを見ることができないでいる。そして、目に見えるかぎりのものを <現実>
と呼んですませている。しかし、そんなものが本当に <現実> と呼ぶに値するのか。 『英語の授業』には、異界から回帰する死者たちがあふれている。例えばこんな風に。
『英語の授業』には、異界から回帰する死者たちがあふれている。例えばこんな風に。 『英語の授業』は、このほど茨城文学賞を受賞した。詩人・塚本敏雄の実力を熟知した電藝読者にとって、彼がどんな賞の栄誉に浴しようが、いまさら驚くようなことではない。ただ、私たちはいま現に生成し、常に新たな誕生をつづける詩人の姿を目の当たりにしているのだ。その生成の現場に、たまたま共に居合わせることができた僥倖を喜ぼうではないか。
『英語の授業』は、このほど茨城文学賞を受賞した。詩人・塚本敏雄の実力を熟知した電藝読者にとって、彼がどんな賞の栄誉に浴しようが、いまさら驚くようなことではない。ただ、私たちはいま現に生成し、常に新たな誕生をつづける詩人の姿を目の当たりにしているのだ。その生成の現場に、たまたま共に居合わせることができた僥倖を喜ぼうではないか。