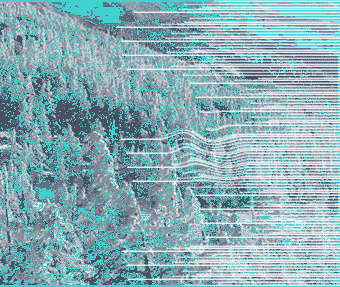|
3.
結局、大家の息子というのは、髪の毛の薄い中年男で、身なりはラルフローレンのスーツだのカルチェの時計だのと、いかにもいかにもなのだが、帰宅して着替えるとトランクスで家中うろつきまわるし、しょっちゅう響きわたるおなら、風呂の鼻唄というオヤジ全開ぶりで、家でカジュアルな服を着ていても一分の隙もないキャリアウーマン風の奥さんにたしなめられている様子が伺えて、それはそれでほほえましく幸せそうだった。 |
|
|
ちょうど夏期休暇に入る直前の前期試験中で、そのころまでには、周囲は何とはなしに要とすずねをカップルとみなすようになっていたが、いまだ決定的なことは何一つ起こってなかった。 高価な器で自家焙煎のおいしいコーヒーを飲ませるという大学通りの喫茶店でノートを写させてもらっていた要に、ジノリのカップを持ったすずねは言った。 「例の、毛糸玉の、そろそろ行こうかな、と思うんだけど。カナ君、バイト、八月からだって言ってたでしょ」 当然のように二人で行くのだなと要は思った。そしていよいよかなと、水色の女の子には悪いけれども、すずねとの関係が一歩進むのではないかと、そちらのほうのことを要は想像した。 「それでね、もう泊まるとこ、とっちゃった」 とすずねが差し出したパンフレットを見ると、それは「県立青少年自然の家」のもの、読むと男女別室だという。 「なーんてね……」 シャープペンシルを宙に浮かせたまま惚けたような要の顔をまじまじとみきわめてから、あらためてすずねは雑誌を取り出した。 「冗談よ。見て。これこれ、素敵でしょ」 すずねが差し出したページにはマーカーで大きく丸をつけてあって、そこで紹介されている宿はすずねの好みを如実に表している。 <イングランドの農家を移築して> <客室はロマンチックな四柱ベッド。ラベンダーの香のする上質なリネンは素敵な夢を見せてくれるでしょう> <家具は十九世紀イギリスのオークのアンティーク> <フレッシュな乳製品と自家製ハーブをふんだんに使った食事> |
|
|
見ると、草原の真ん中に灰色の石積みに幾つも煙突の立った白い窓枠の建物とともに、渋い色合いの室内や真鍮と白い陶器のバスルーム、さまざまな料理の写真が載っている。 ● 八ヶ岳の麓のだれもいない夕暮れの草の丘をほどけながら転がり落ちていく毛糸玉を二人で見送って―― (了)
|