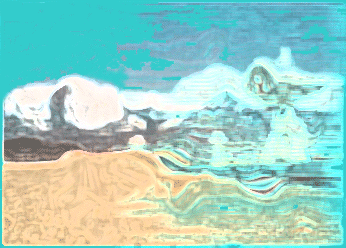|
「とにかく、これをほどいてしまわなきゃ」 |
|
|
小学生のころそんなことを手伝わされたような記憶がある。母親は物を大切にする人で、前に編んだ自分のセーターやら、赤ん坊のころの姉の出雲や要のボレロやらをほどいて、新しく急に背の伸びた要のセーターを編み直したりしていたものだ。そんなことを思い出しているうちに、大きな毛糸玉ができあがった。 「ふうっ、終わった」 すずねは大事そうに玉をかかげ持った。ところどころ黄ばんで、あわあわとけばだったその玉は、深い後悔に覆われていてもどこか真摯で甘い想いで紡がれた繭なのだ。 「──わたさなきゃ」 要は、自分の唇が、考えるよりも先に言葉を紡ぎだしていることに気がついた。 「そうね。だから今度……清里に行きましょう」 すずねの声も、なんだか熱にうかされているようだ。 八ケ岳南麓、清里高原。 アイスクリームと、ハーブと、ジャムと、京風らーめんの高原。 ――そう、そこに、わたしの恋の。わたしの、 「思い出の」また口が勝手に喋る。 「……? そして、ウンカイの浜辺でわたしましょ」 ウンカイって何だ? ああ。そうだ、そうだ。 「あのとき二人で見た朝日に輝く雲の海の」 「……カナ君?」 「ん?」 「……うれしい」 |
|
|
すずねは、毛糸玉を雛のように抱きしめて、まん丸い目からぽろぽろと涙をこぼしていた。
|