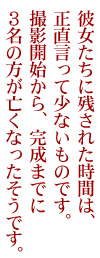<忘れたいこと> と
<忘れちゃいけないこと> の狭間で
今回は『ひめゆり』というドキュメンタリー映画をご紹介致します。沖縄戦における <ひめゆり学徒隊> の真実の姿を、22名の生存者へのインタビュー映像と当時の沖縄戦記録映像を織り交ぜながら描き出した、全3章・合計130分の力作です。
<忘れたいこと> と
<忘れちゃいけないこと> の狭間で
今回は『ひめゆり』というドキュメンタリー映画をご紹介致します。沖縄戦における <ひめゆり学徒隊> の真実の姿を、22名の生存者へのインタビュー映像と当時の沖縄戦記録映像を織り交ぜながら描き出した、全3章・合計130分の力作です。
太平洋戦争末期の1945年3月23日。米軍は沖縄本島への艦砲射撃・空爆を開始。同日、18名の教師に引率された15〜19歳の <ひめゆり学園> (女師・一高女)の女学生222名が戦場動員されました。この240名の一団を <ひめゆり学徒隊> と言います。
「赤十字の旗の下だから安全。そこで負傷兵の看護をすることが私たちの仕事」
と思い込んでいたひめゆり学徒の面々でしたが、実際は、砲弾が飛び交う、常に死と隣り合わせの過酷な戦場に放り込まれることとなったのです。
冒頭に掲げた言葉は、生存者の宮良ルリさんが、その沖縄戦の惨状を思い出しながらカメラに向かって搾り出したものです。
伊原第三外科壕に配属された彼女でしたが、やがて、絶望的な戦況の中で、壕の全員に解散命令が出されます。ささやかなお別れ会を行った後、皆が壕の外に出ようとしたその時、壕が米軍に見つかってしまいます。米軍は壕の中にガス弾を投入。「息が出来ない!」「苦しい!」「死にたくない!」「先生助けて! お母さん助けて! お父さん助けて!」…… 壕のあちらこちらから悲痛な叫び声が上がり、未曾有のパニック状態となったそうです。宮良さんは、やがて意識を失い、ようやく目覚めたのが3日後。周囲には兵隊や学友の死体が累々と転がり、腐臭と蛆みまみれながら、彼女は、更に4日間を飲まず喰わずで過ごす事になります。その状態を指して、彼女は <阿鼻叫喚> という表現を用いたのでした。
<阿鼻叫喚> 。この言葉は、私の心をグサッと突き刺しました。なんと凄絶な表現であることでしょう。私にとって、普段、 <阿鼻叫喚>
という言葉は、文学的、あるいは映像的イメージを漠然と喚起する言葉として受け止めています。
<想像を絶するほどむごたらしい状況> という意味合いとして、 その言葉を正しく理解しているつもりではいますが、どうも思考が追いつかない。およそ、私を含めて、戦後生まれの人間にとって、
<阿鼻叫喚> という言葉が当てはまる体験をした者など、ほとんど存在しないでしょう。他国へ渡り、戦場カメラマンとして活動している方や、戦場をリポートしたテレビ関係者・記者などは別として、日本に暮らす人々は、おそらくこれほど無惨な経験はしたことがないでしょうね。
しかし、太平洋戦争の只中では、日本国民の大部分が、こういった <阿鼻叫喚> の状況を実際に体験したわけです。東京大空襲・大阪大空襲・硫黄島決戦などなど。太平洋戦争末期は、日本中が戦火に包まれました。前回採り上げた『ヒロシマナガサキ』で描かれた原爆投下時の広島・長崎も、正に <阿鼻叫喚> といった状況だったでしょう。
中でも、沖縄線は、その <阿鼻叫喚> の地獄絵図に、非戦闘員が多数巻き込まれたものでした。ひめゆり学徒も、紛れもない非戦闘員です。年端もいかぬうら若き乙女たちが、戦場に狩り出され、尊い命を多く散らせていったわけです。
最終的に、沖縄陸軍病院に配属されたひめゆり学徒隊240名(生徒222人・教員18人)の内、136人(生徒123人・教員13人)が死亡。実に半数以上が尊い命を奪われたというわけです。また、ひめゆり学徒隊に参加しなかったひめゆり学園の沖縄戦における死亡者は91人(生徒88人・教師3人)とされており、合計で227人(生徒211人・教員16人)に上ります。その一人一人が、それぞれの <阿鼻叫喚> を味わったはずです。宮良さん以外の証言者の方々も、作中で、沖縄戦での <阿鼻叫喚> の模様を説明していて、その酸鼻極まる状況に胸が痛くなったものです。
さて、しかし、今になってなぜ『ひめゆり』なのでしょう?
これまでにひめゆり学徒隊を題材にした書籍や映画・TVドラマが多数作られましたが、生存者にとってすれば、それは誤解や誇張に満ちたものだったそうです。
例えば、 <ひめゆり部隊> という言葉がよく用いられますが、これは間違いです。そんな言葉は当時使用されていなかったのです。それが、現在、さも当時から存在した言葉であるかのように誤って伝わっているのです。正しくは <ひめゆり学徒隊> なのですね。
「そんなのどっちでもいいじゃないか?」と思われる方、きっといらっしゃることでしょう。しかし、ここははっきりと言いましょうね。「よくありません」と。
正しい知識を得ることは大事なことです。小さな誤解が、更に大きな誤解に繋がっていくことは往々にしてありますし、それはやがて、真実を見失うことにもなりかねません。そういった危惧もあって、22名の生存者の方々は、本作に協力したのでしょう。
生存者の1人である本村つるさんはこう話します。
【戦後、ひめゆりを題材に小説や映画が数多く世の中に出ましたが、それらのほとんどがフィクションです。実は、私たちはそれらが出るたびに落胆し、憤慨していました】
彼女が不満を感じた作品が、世の人々に対して、感動を与え、反戦の心を植え付けた功績はあるでしょう。その点を否定する気は、私にはありません。そういった作品が、尊く正しい意識を芽生えさせるきっかけとして機能したのならば、それはまた素晴らしい事だと思うからです。
しかし、真実を知る者にとっては、間違った認識の下に作られていたり、キレイ事だったりする部分がどうしても目に付く。「ここは違う!」「こんなもんじゃなかった!」ということでしょう。ならば、私としては、その真実をこそ知りたいと思うのです。
とはいえ、彼女たちは、戦後、なかなか自身の体験を、自身の口で語る事がなかった。その機会がなかったという人もいるでしょうが、語る気になれなかったという方もいらっしゃるでしょう。事実、今でも、当時のことを一切語らないという姿勢を貫いている方もいらっしゃいます。
生存者は、きっと皆、<忘れたいこと> と <忘れちゃいけないこと> の狭間で苦悩してきたのでしょうね。そうした中、生存者の中で22名の方が、この『ひめゆり』という作品のために、カメラの前で当時の模様を語って下さったというわけです。
その取材期間は、1994年から2006年にかけて、実に13年に及んだと言います。証言の収められたテープは100時間以上という膨大な量になりました。
本作の監督は1964年生まれの柴田昌平。言うまでもなく <戦争を知らない世代> です。撮影担当として4人がクレジットされていますが、彼らも戦後の生まれ。
クランク・イン前に、監督に対して、撮影担当の1人である澤幡正範がこう尋ねたそうです。
「証言の記録作業でテープは何本用意するの? 何人の人に話しを聞かせてもらえるの?」
監督はこう答えました。
「テープは50本。話を聞かせてもらえるのは10人以上」
それを受けて、澤幡はこう監督にお願いしたと言います。
【可能ならばテープを100本欲しい。なぜならば、語ってくれる彼女たちがもう話すことができないと言うまでテープを廻し続けたい。収録の途中で、もう充分ですと、こちらからは言ってはいけないのではないか。本当に彼女たちが語り尽くすまでじっと耳を傾けるのが、この仕事の基本姿勢じゃないのか】
監督は、この言葉を受けてテープを100本用意してくれたそうです。
この <作り手の聴く姿勢> が、22名の証言者にとって堪らなく嬉しいものであったことは想像に難くありません。本作のパンフレットに記載されている彼女たちのメッセージには、 <若い人> に向けた言葉が非常に多いのですが、これは、これからの日本を、これからの世界を担っていく人々に対しての切実な願いを込めてのものでしょう。
<戦争を知らない世代> が、『ひめゆり』という作品を企画・制作・上映してくれる。過去を風化させることなく、自身の経験を語ることで、それを受け止める人々が現在を見つめ、そして未来への糧としてくれることをこそ、彼女たちは望んでいるわけです。
彼女たちに残された時間は、正直言って少ないものです。撮影開始から、完成までに3名の方が亡くなったそうです。残る19名の方々も、近い将来この世からいなくなってしまう。そうなる前に、これからの将来のために伝えておきたいという思いがありがたいではありませんか。
人間は愚かな生き物です。喉下過ぎれば、また愚かな行動に出てしまう事だってあります。このことは、歴史がそれを証明しています。そうでなければ、とっくにこの世から戦争なんてなくなっているはずですよね? そう、人間は本当に愚かな生き物なのです。
しかし、それを止めること。これも人間にしか出来ないことです。彼女たちが<忘れたいけれど忘れちゃいけないこと> を話してくれた重みを、 大いなる感謝と共に受け止め、そこから生まれる気持ちをいつまでも忘れることなく肝に銘じ、そして広く伝えていく事こそ、現在、平和を享受し得ている我々の責務なのではないでしょうか? 彼女たちの経験が生み出したとも言える教訓と平和を、一過性のものとすることなく、永続的に保っていくことが何より肝要です。
本作、先に書いた <阿鼻叫喚> の模様の他にも、印象的なエピソードが多数語られます。惨たらしい中にも、感動的なエピソード・人間の温かみを感じるエピソードもあり、思わず涙が頬を伝ったものです。「北海道の鈴蘭のエピソード」「『俺は君たちを殺せない』エピソード」などなど、全部ご紹介したいのですが、紙数もありませんし、なにより、この秀作を、実際に皆さんのその目でご覧頂きたく思います。
『ひめゆり』という秀作を鑑賞し、その上で皆さんにご紹介できることを心から誇りに思います。
さて、次回の銀ナビは特集企画第3弾。『TOKKO-特攻-』という作品をご紹介致します。こちらもご期待下さいね。
P.S. 本作をご紹介するにあたって、配給元であるプロダクション・エイシア様より、パンフレット・プレスシートといった文字資料の提供を頂きました。厚く御礼申し上げます。
ひめゆり http://www.himeyuri.info/
「忘れたいこと」を話してくれてありがとう
2006 130分 監督:柴田昌平 撮影:澤幡正範/川崎哲也/一之瀬正史/川口慎一郎
東京:ポレポレ東中野にて9月14日までアンコールロードショー中
大阪:十三第七藝術劇場にて8月17日まで1日2回公開
詳しくは公式HPにてご確認下さい
2007年8月13日号掲載