

| キ ム チ p r o f i l e | ▲ |
| ▼ | |

 |
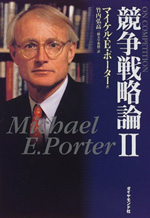 |
古今東西のさまざまな人たちがさまざまなことを言ってきたが、その中で気に入っている言葉の一つにジョン・メイナード・ケインズの次のものがある。「長期においては」とケインズは言う、「われわれは皆死んでしまっているはずだ。」
どうやらケインズは、「長期的にみれば」市場が均衡状態にいたる傾向を持つということ自体は否定せずに、しかし長期的にわれわれ全員が死滅する前に、現実的に目の前に生じている不均衡を解決する方法を考えなくてはならないと思ったようだ。この言葉が使われた正確な意味を理解していようといまいと、この言葉には、理論的な正しさと現実との間にあるギャップを嗤うユーモアを感じる。
しかしながら、市場=均衡=公正という公式が成立するのか否か(そもそも均衡した市場は公正をもたらすのか)、市場=均衡は成立するのか(はたして市場は、均衡する傾向を本性として持つものなのか)は、議論の余地のある問題であり、何よりもそれは抽象的な議論でしかなく、現実に市場=均衡は存在していない。
現実的に、さまざま不均衡が存在するからこそ、企業は新しい市場=業界に参入したり新規事業を起こすのであり、あるいは帰属の市場=業界の中で新技術を導入して新商品を投入することによって「より多くの」利潤を獲得しようとするのである。
例えば、マーケティング理論の大御所であるマイケル・E・ポーターは、市場=業界の優劣を判断するために、「ファイブ・フォーシズ」という分析概念を提唱している(『競争優位の戦略』)が、そこでは「業界の競争関係」、「新規参入の脅威」、「供給業者の交渉力」、「顧客の交渉力」、「代替品・サービスの脅威」が5つの要因が、企業の帰属している市場=業界が企業にとって熾烈で過酷なものか、あるいは競争の緩やかな「おいしい」業界かを決定する要素として挙げられている。過酷か穏和か(おいしいか)とは、要するに企業にとって利潤が上げられやすいか否かということだ。
ここで例えば、「新規参入」の障壁が高いということは、その市場=業界が仮に他の業界よりも利潤の高い「おいしい」業界であったとしても、例えばその業界に参入するためには大きな設備投資が必要であるとか、あるいはそれこそ政府の規制によって認可を受けなければ参入できないといった事情がある場合に、その市場=業界がおいしい業界であり続けるということをさす。
もちろん、中谷巌や竹中平蔵が目指していることは、そうした参入障壁を取り払って、市場に競争原理を導入することである。競争原理を導入することによって、企業は勝ち抜くために企業努力を惜しまず、イノベーションを繰り返さなくてはならなくなる。それは、消費者の利益に資するだろう。しかし、ここで確認しておくべきことは、市場均衡がもたらすであろう公正さと、企業がそこで本能的に行動する「欲望」との間には正反対のベクトルが働いているということに尽きる。マーケティングとは、マーケットとは正反対のものなのである。
では、そもそも中谷巌や竹中平蔵は、市場の均衡=公正を目指しているのだろうか。それとも、競争的な社会を目指しているのだろうか?
市場が均衡すれば利潤は消えると書いた。一般的には、市場が均衡すると利潤は「一般利潤率」に一致するとされる。では一般利潤率は何によって決定されるのか?その市場の成長率によって決定される。では、市場の成長は何によって決定されるのか?
例えば「国の富」とは何かについて、古今さまざまのことが議論されてきた(『国富論』のアダム・スミスが最初というわけではない)。マイケル・E・ポーターは『競争戦略論Ⅱ』にこう書いている。
国の繁栄は創り出されるものであって、天賦のものではない。国の経済成長性は、古典派経済学が主張するように、天然資源や労働力、金利、通貨価値によって決まるわけではない。ある国の競争力は、その国の産業においてイノベーションを起こし、グレードアップしていく能力によって決定される。 (マイケル・E・ポーターは『競争戦略論Ⅱ』、ダイヤモンド社、竹内弘高訳、5頁) |
では、いったい成長は必要なものなのか?現在のような成長を続けることが、人類にとって命取りであることは、さまざまな環境学者によって指摘されてきた。しかし、何が正しいかという議論はここではおいておこう。
はっきりしていることは、次のことである。少なくとも、公正のためには、成長は必要ない(それが均衡理論の伝えていることだ)。しかしながら、成長しなければ、競争に負け、後塵を拝する結果に陥ることをおそれて、絶え間のない成長と競争の中に人々は身を投じているのである。マーケティングという活動の背景をなしている思想、あるいは欲望とは、そうしたものである。
![]()
| ▲このページの先頭へ |  |