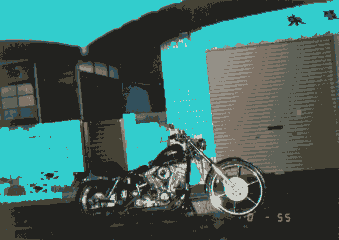|
2.
すずねによれば、彼女は、要と別れてベッドに入り、そして朝目覚めるまで、特段変わったことを経験したわけではなかった。しかし、夜明け頃、まるで母親に揺り起こされたかのような感じがして目が醒めたのだという。もちろんのこと、そこにはだれもおらず、一瞬途方にくれたが、頭がはっきりするにしたがって、一つの考えが沁みとおるように伝わってきたのだ。まるで親友からの大事な頼まれごとのように。女の子同士の内緒話、打ち明け話のような、やさしくてくすぐったい感覚をともなって。ただ、あまりに揺り起こす手の感触がリアルで、いつまでもその感じが残っているので、彼女はやむにやまれず要に電話したのだという。 |
|
|
生田目祥子は要もキャンパスで何度か見かけたことのある女の子だったが、背が高くて、そのころ深夜テレビなどでブームになって大いにもてはやされた
<いわゆる女子大生> そのものの派手な女の子で、もっぱら自分とは縁のない人種と決めつけた要は、話を交わしたこともなかった。目の前のすずねとはまったく対照的で、すずねが彼女と知り合いだということさえ、少々意外な感じがした。 「彼女ね、自分のアパート帰りたくないものだから、あちこち泊まり歩いてて、ほとんどノイローゼ状態になっちゃって、いつもの取り巻き連中も、ショーコおかしいって言いはじめて、よそよそしくなっちゃって、とうとう、もうどこも泊まるあてがなくなって、えらく思い詰めてるもんだから、うちに泊めたのよ。それでいろいろ聞くと、アパートに何か出るっていうじゃない」 祥子がここで夜を過ごしたのは、ほんの一週間程度だったらしい。 |
|
|
引っ越してきたその夜から怪奇現象、幽霊屋敷とくればおきまりのラップ音、勝手に閉まる戸、台所で水を使う音。それらにいっぺんに遭遇して眠れぬ夜を過ごした翌朝、無理やり、気のせい、古い家のせい、と決めつけ、気を取り直して大学に行ったが、次の夜には家中の床をのたくるスライム状の物質に足を取られ、大家の子供の家だという隣家に駆け込んだものの、相手にされず、残る三軒も堅くドアを閉ざしたまま。恐る恐る戻った部屋は何ごともなかったように静まりかえり、異常な物質も姿を消していて、とはいえもうその部屋で眠るつもりは露と消え、ボーイフレンドの家に転がりこんだものの、その彼は自分から別れ話を持ち出しかけたばかりでタイミングが悪く、新しい彼女からのけたたましい電話攻勢にめげて一晩で飛び出すと、もう引っ越すしかないと決心し、とりあえず実家に無心に帰ろうかどうしようかというところですずねに出会ったというわけだ。 |